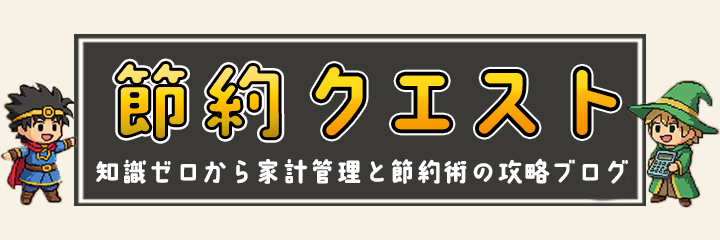「家計簿の費目ってどう分けるの?」に共感するあなたへ
家計簿を始めるときに多くの人が悩むのが「費目の分け方」です。
「食費、日用品、光熱費、美容、交際費…細かくしないといけないの?」
「でも多すぎると入力が大変で続かない」
僕自身も最初は10以上の項目を作っては、途中で「どれに入れればいいかわからない」と挫折してきました。
実際、総務省「家計調査(2024年)」によれば、家計簿が1年以上続く人の割合は全体の3割未満。その理由の1つが「管理が細かすぎて疲れてしまう」ことです。
そこで今回紹介するのが「費目は3つでOK」というシンプル管理法。
食費
固定費
その他
この3分類に絞るだけで入力が驚くほどラクになり、続けやすさが格段にアップします。
結論:家計簿は「食費・固定費・その他」で十分
費目を細かく分けるのは、正確に見える反面「継続性」を失いやすい罠です。
家計簿の目的は「家計の全体像を把握し、改善につなげること」。細かい数字の精度よりも、まずは続けられることが優先です。
例えば「外食は食費?交際費?」と悩むと、そこで手が止まってしまいます。でも「食費」に全部まとめてしまえば悩みゼロ。後から「外食多めだったな」と気づければ十分です。
僕も以前は「家計簿は正確さが命」と思っていましたが、実際は「続けられる方が効果的」だと痛感しました。数字はざっくりでも、見える化することで行動は変えられるのです。
【関連記事】:家計簿を習慣化するコツ5選|ズボラでも無理なく続けられる方法
なぜ3分類でいいのか?シンプル管理のメリット
ではなぜ3分類だけで十分なのか。理由は大きく3つあります。
第一に「迷わない」こと。項目が少なければ、「どこに入れよう?」と悩む時間が減ります。これが続けやすさに直結します。
第二に「全体が見える」こと。食費と固定費で大部分を把握できるため、生活費の傾向が一目瞭然になります。例えば「固定費が高すぎて自由に使えるお金が少ない」と分かれば、通信費や保険の見直しに動けます。
第三に「改善しやすい」こと。費目を増やすと「どこを減らせばいいか」が分かりにくくなりますが、3分類なら「食費を減らそう」「固定費を削ろう」とシンプルに考えられます。
僕も3分類に変えてから「毎月どこを改善すべきか」がすぐに見えるようになり、自然と節約行動に移せました。
実際の振り分け例|何をどこに入れる?
「3分類にすると曖昧になりそう」と心配する人もいるでしょう。そこで、実際の振り分け例を紹介します。
食費:スーパーの買い物、外食、カフェ代、飲み会代
固定費:家賃、光熱費、通信費、保険料、サブスク代
その他:日用品、趣味、娯楽、交際費、医療費、衣服
このくらいざっくりで十分です。「あれはどこに入れれば?」と悩んだら、とりあえず「その他」にまとめればOK。
実際に僕も「交際費か食費か迷う支出」を毎回その他に入れていますが、全体像は把握できるので困ったことはありません。
【関連記事】:家計簿が続かない理由と解決法|挫折しないためのシンプル管理術
“費目3つ”家計簿で得られる効果とは?
実際に「費目3つ」家計簿を取り入れると、どんな効果があるのでしょうか。僕自身の体験や、周囲の実例から整理すると大きく3つのメリットが見えてきます。
まず「数字が頭に入りやすい」こと。10項目以上に分けると、集計したときに全体のイメージがつかみにくいのですが、3分類ならパッと見で「今月は食費が高いな」と理解できます。僕もこれに変えてから、月の支出を数字ではなく“感覚”としてつかめるようになり、節約行動に直結しました。
次に「改善ポイントが明確になる」こと。例えば、固定費が収入の半分近くを占めていたら「保険や通信費を見直そう」という行動につながります。逆にその他費用が膨らんでいたら「趣味や日用品を見直そう」と判断できます。
さらに「達成感が得やすい」ことも大きな効果です。支出を3つだけ管理していると「今月は食費を5,000円減らせた」と一目でわかり、小さな成功体験が積み重なります。心理学的にも、この“小さな成功”が習慣化を助けるのです。
実例紹介|“費目3つ”で続けられた人たち
ここでは、実際に「費目3つ」に切り替えて成功した人たちの体験を紹介します。
30代会社員のAさんは、以前は12項目の家計簿をつけていました。しかし「入力が面倒で1か月も続かない」と悩んでいたそうです。そこで「食費・固定費・その他」の3つに切り替えたところ、半年以上続けられ、年間で20万円以上の節約に成功しました。
20代大学生のBさんは、スマホアプリで10項目に分けて入力していましたが、アルバイトや学業で忙しく、途中でやめてしまったとのこと。しかし、3分類にしてからは「空き時間にまとめ入力」が可能になり、毎月の仕送りを無理なく管理できるようになりました。
40代主婦のCさんは、家族の生活費を管理するために詳細な分類をしていました。しかし「毎日の記録に疲れた」と挫折寸前に。そこで3分類に切り替えたところ、無駄遣いを見つけやすくなり、夫婦で「食費をあと5,000円減らそう」と具体的な話し合いができるようになったそうです。
このように「費目を減らす」ことは、ズボラな人だけでなく忙しい人や家族世帯にとっても効果的です。
形式別に取り入れる“費目3つ”の工夫
「紙」「アプリ」「エクセル」それぞれで、費目3つを取り入れる工夫を見ていきましょう。
紙の場合、ノートに「食費」「固定費」「その他」の3つの欄を作るだけで完結します。1ページに1か月分をまとめる形式にすると、1枚で全体を把握できるので視覚的にも分かりやすいです。
アプリの場合、初期設定で費目を細かく作るのではなく、あえて3つに統一しましょう。アプリは自動分類機能もありますが、逆にそれが複雑さの原因になることもあります。僕はアプリの設定を3分類にしただけで、操作が格段に楽になりました。
エクセルの場合は「食費・固定費・その他」の3列だけ作成すればOKです。SUM関数で合計を出せば、1か月の支出が一瞬でわかります。細かい数式を入れる必要はなく、テンプレートを使えばさらに効率的です。
【関連記事】:初心者向け家計簿の書き方ガイド|紙・アプリ・エクセルの違いと選び方
比較表|従来型家計簿と“費目3つ”家計簿の違い
従来型とシンプル型の違いを表に整理しました。
| 項目 | 従来型家計簿(10項目以上) | “費目3つ”家計簿 |
|---|---|---|
| 継続率 | 低い(3割未満が1年以上継続) | 高い(半年以上続く人多数) |
| 入力時間 | 毎日10〜15分 | 週1回5分程度 |
| 迷いの有無 | 項目選びで迷いやすい | 迷いゼロ |
| 改善のしやすさ | データが細かすぎて分析困難 | 食費や固定費の改善が一目瞭然 |
この比較を見ても、“シンプル管理”が続けやすさのカギであることが明らかです。
“費目3つ”で管理する実践ステップ
では実際に、どのように「費目3つ」で家計簿を運用していけばよいのでしょうか。ここでは初心者でも迷わずにできるステップを紹介します。
まず最初に行うのは「財布とレシートの整理」です。買い物をしたらレシートを財布や袋にためておき、週末にまとめて家計簿に入力します。この時点で「食費」「固定費」「その他」のどれに分類するかだけ決めればOKです。細かいメモや品目まで残す必要はありません。
次に「1か月の収支を振り返る」ステップです。合計を出したら、どの費目に一番お金が流れているかを確認します。もし食費が大きければ「外食を減らす」、固定費が高ければ「保険や通信費を見直す」といった改善策を考えます。
最後に「次月の目標を立てる」ことが重要です。たとえば「食費を先月より5,000円減らす」といった具体的な数字を設定すれば、翌月の行動につながります。
僕自身、この3ステップを回すだけで「ただの記録作業」から「改善のサイクル」へと進化し、自然に節約体質が身につきました。
心理的トリックを使った継続のコツ
人間の行動は「楽しいこと」や「成果が見えること」で習慣化しやすくなります。家計簿も、この心理的な仕組みをうまく取り入れると挫折を防げます。
ひとつは「見える化のご褒美」です。家計簿アプリならグラフやチャートを活用し、支出が減った月には「緑色の表示」で視覚的に達成感を得られるように設定しましょう。紙やエクセルの場合も、達成した項目に色を塗るなど、視覚効果を使うとモチベーションが高まります。
もうひとつは「ご褒美貯金」です。節約できた分の一部を、好きなものに使うルールを作ります。例えば、食費を5,000円減らせたら、そのうち1,000円で美味しいスイーツを買う。これだけで“節約=我慢”から“節約=楽しみ”に変わります。
僕も「固定費を見直して浮いた分の1割を趣味に回す」ルールを設けています。すると「節約すればするほど趣味も楽しめる」というポジティブな循環が生まれるのです。
“費目3つ”でも挫折する?失敗しやすい落とし穴と改善策
もちろん「費目3つ」でも挫折する人はいます。その理由と改善策を見ていきましょう。
まず多いのが「記録をため込みすぎる」ケースです。週1回なら続けやすいですが、1か月分をまとめて処理しようとすると面倒になりやめてしまいます。改善策は「最低でも週1回は入力」。この小さな習慣が大切です。
次に「分類を迷って止まってしまう」ケース。例えば「医療費は固定費?その他?」と考えすぎて記録が進まなくなります。これも解決は簡単。「迷ったらその他に入れる」と割り切るルールを決めること。正確性より継続性を優先しましょう。
最後に「目的を見失う」こと。数字を眺めるだけで改善につなげなければ、家計簿はただの手間です。ここで「何のために続けるのか」を常に意識することが大切です。
実際の改善事例|“費目3つ”で支出が変わった
最後に、僕自身と知人の改善事例を紹介します。
僕は「固定費」が収入の半分近くを占めていた時期がありました。家計簿で見直すと「スマホ代と保険料」が高すぎると判明。格安SIMに乗り換え、不要な保険を解約しただけで月1万5,000円の節約に成功しました。
知人のDさんは「食費」が収入の3割以上を占めていました。家計簿で分析すると、毎日のコンビニ利用が大きな原因。週末にまとめ買いへ切り替えたところ、月1万円以上の削減に成功したそうです。
このように「3分類」というシンプルな仕組みでも、改善のきっかけは十分に見つかります。
まとめ|家計簿は“シンプルに続ける”が最強の方法
ここまで解説してきた通り、家計簿の目的は「正確な記録」ではなく「お金の流れを理解して改善につなげること」です。
結論として、大切なのは次の3点です。
費目は3つで十分
細かさよりも継続性。食費・固定費・その他だけで家計の全体像は十分把握できる。
続ける仕組みを作る
週1回のまとめ入力や「迷ったらその他に分類」で、挫折のリスクをなくす。
改善に結びつける
記録して終わりではなく、気づきを「固定費の見直し」「外食を減らす」など行動に変える。
僕自身、何度も家計簿で挫折してきましたが、この“3分類ルール”を取り入れたら驚くほど長続きしました。そして月1万円以上の節約に成功し、旅行や趣味に回せるお金も増えました。
よくある質問(FAQ)
Q. 「食費」と「交際費」は分けた方がいいですか?
A. 初心者はまとめて「食費」でOKです。大きな流れが把握できれば十分。必要になったら細分化すれば大丈夫です。
Q. 医療費や教育費はどこに入れればいいですか?
A. 迷ったら「その他」で問題ありません。重要なのは続けること。詳細管理は習慣化してからでも遅くありません。
Q. 3分類だと改善点が見えにくくないですか?
A. むしろ逆です。支出の大きな傾向がはっきり見えるため、「どこを減らすか」がすぐに分かります。
関連記事リスト
【関連記事】:家計簿を習慣化するコツ5選|ズボラでも無理なく続けられる方法
【関連記事】:家計簿が続かない理由と解決法|挫折しないためのシンプル管理術
【関連記事】:家計簿をつける意味ってある?お金が貯まる人の考え方と活用法
【関連記事】:初心者向け家計簿の書き方ガイド|紙・アプリ・エクセルの違いと選び方
【関連記事】:やりすぎ節約は逆効果!家計を圧迫するNG習慣ランキング10選